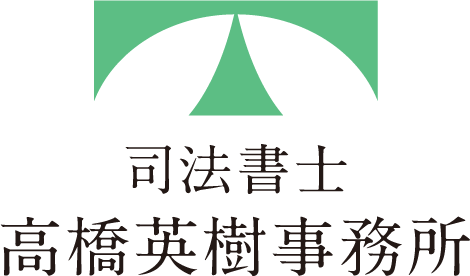山手に出かけると風が心地よい季節になりました。
旧富士町・旧三瀬村方面では山野草が楽しめます。

アキノタムラソウです。
シソ科で、山野草が趣味の方が栽培していることもあります。
拡大してみました。

学名は、Salvia japonica で、「日本のサルビア」です。
記載者は、以下で何度か登場するスウェーデンの医師ツンベルクです。
彼の名は、“Thub.”と略して使われます。
そのくらい記載した種類数が多いのです。
ついでに述べると、今はトゥーンベリと表記することが多いかもしれません。
あの環境活動家グレタさんはThunberg姓なのです。
続いてはツリフネソウ科ツリフネソウImpatiens textorii です。
これもまた栽培されることが多い種でしょう。
ツリフネソウは道路脇にちょっとした群落を形成していました。
記載者はミクェルというフランスの植物学者。学名表記では“Miq.”と略されます。

三番目は、薬草としても知られているフウロソウ科ゲンノショウコ Geranium thunbergii
学名からは、ツンベルク(C.P.Thunberg)に献名されたものだとわかります。
チョウでは、ナガサキアゲハの日本亜種が ssp.thunbergii です。
ナガサキアゲハ同様にシーボルトが記載したのだろうと思ったら、案の定。
Geranium thunbergii Siebold et Zucc ですので、ツッカリーニとの共同記載です。
決して珍しくはないのですが、小さいために目にとまりません。
ツッカリーニはドイツの植物学者です。

最後は、オミナエシならぬオトコエシ Patrinia villosa
オミナエシ科です。

標高が低い場所ではまだ花が咲いていました。
この株は花が終わって果実ができていました。
オトコエシは漢字で書くと「男郎花」。
けっして「男壊死」ではありません。
学名は、正式にはPatrinia villosa (Thunb)Juss
最初はツンベルクが記載して学名が決まり、その後にジョシュ―が変更したようです。
*ここに登場した欧州の学者たちは、全員が江戸時代の人です。