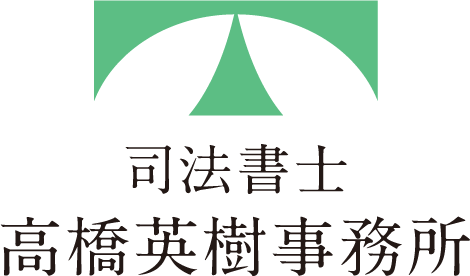治部煮という料理があります。
石田治部少輔三成にちなんで治部煮なのだろうか?
だが、それでは江戸時代には禁断の料理になってしまう。
そういう疑問を抱いていましたが、違うようです。
使われる材料も様々らしく、鴨肉や牛肉も選ばれることがあります。
今回は、冷蔵庫にある食材を使うことを前提に使いました。
鶏もも肉、レンコン、ニンジン、オクラ。
これにだしつゆを作った際の「だしがら」である干し椎茸。
秋なのでキノコを増やそう。
エノキタケ、マイタケ、シメジを買い足しました。
そぎ切りにした鶏肉には片栗粉をまぶします。
筑前煮では材料を炒めますが、この料理に「炒め」はありません。
だしつゆを作った際のだしがらを水煮して作った「二番だしつゆ」にオクラを除く材料を投入。
だしつゆを吸った干し椎茸から濃い味のだしつゆが染み出します。
よって、全体の味をみながらの調整は必須。
煮上がる前にオクラを入れて、軽く火が通るように。
これでできあがりです。

茹でた水菜や小松菜などを添えるといろどりよく盛り付けることができます。
肝心の料理名のいわれですが、諸説あるようです。
加賀前田家に預けられていた高山右近が欧州料理を伝え、結果的に治部煮になった。
「しふしふと煮る」がなまって治部煮になった。
いずれでもよさそうな気がします。
だしつゆが都合よく家にない場合は、一番だしをひき、味醂と酒を使えば大丈夫。
その場合は、醤油で味付けをします。
今回は、水煮した「二番だしつゆを早く使うという目的もありました。
水が入っている以上、日持ちしないのです。
無駄にせずに早めに使い切ろうと思った次第です。
里芋やさやいんげん、豆腐なども使えると思います。