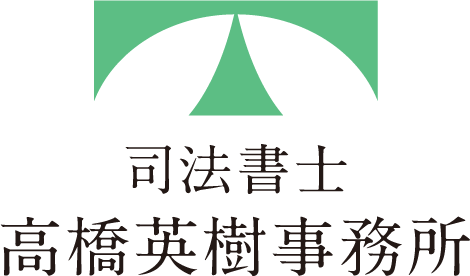私が司法書士試験に合格して間もない研修の時期のことでした。
ある先輩司法書士が、「この本が一番よく書いてある」と示したのは・・・
なんと、受験用のアンチョコ本でした。
「ハァ~?」
と声が出そうなのを抑えました。
さすがにそれはないだろう。
裁判所と話す際に参考文献として使えるか?
そもそも、本当に「よく書いてある」のか?
「ちゃんとした本」と比較したら穴だらけなのがわかるはずだが・・・
どうやって「一番」と認定したのか?
気になるところです。
受験用アンチョコ本が「よく書いてある」ように感じられる。
これには理由があるのです。
少なくとも、試験に出ることは網羅的にとりあげられています。
多くの受験生はアンチョコ本を使って合格できています。
試験レベルであれば、アンチョコ本でもなんとかなってしまうのです。
でも、肝心の基本的な考え方や法律全体に通ずる思想などは説明されていません。
書き手が研究者ではない以上、比較法的な視点も一切ありません。
立法や改正の経緯などの説明もありません。
試験ではそこまで問われないからです。
結果的に、知識の羅列というレベルの本ができあがります。
そういう本を重用するかどうか?
でも、合格後にはさらなる勉強が必要であることに気づかねばなりません。
表面的な知識を頭に入れておいても、様々な事件で応用できないのです。
試験でクイズ的に問われる場合には知識を吐き出すだけで対応できます。
しかし、生の事件を扱うのは無理なのです。
アンチョコ本どまりの人は大丈夫なのだろうか?
実は、私は心配しているのです。
私も受験用アンチョコ本を使いました。
でも、それは試験用の知識を整理するためにだけ。
整理は整理でしかありません。勉強とは呼べないでしょう(作業みたいなものです)。
勉強には「ちゃんとした本」を使います。
今もそう。
使うのは「ちゃんとした本」のみです。
アンチョコ本はとてもではありませんが、まったく使えません。
私は、合格後に全部廃棄しました。
見直す可能性が皆無だからです。
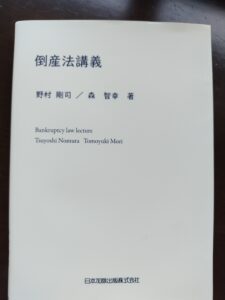
★ 倒産法は司法書士試験の科目ではありません。
それゆえアンチョコ本は存在しません(司法試験用のアンチョコ本はあります)。
伊藤眞教授の「破産法・民事再生法」(有斐閣)は通読するには大部すぎる。
となると、実務家2名(野村弁護士は司法試験考査委員を経験)の手になるこの本は使い勝手がよいのです。
実務家が書いたものではあるものの、制度趣旨などの説明が十分です。
そのうえ薄いので再三読み返すことも苦になりません。
破産に関しては、条文をあまり読まずに書式にばかり目を向ける傾向があります。
しかし、最低でもこの1冊くらいは読みこなさないと、担当する裁判所書記官と対等に話すことができないでしょう。