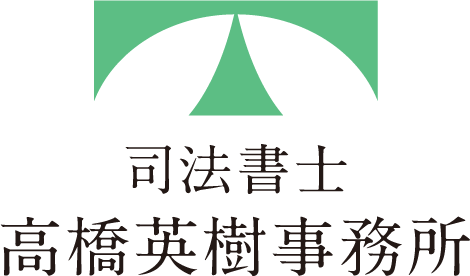「当社は実力本位を旨とし、実力のある方には早い段階から
プロジェクトリーダーをお任せ・・・」
というような採用案内をよく目にします。
これを読んだ人の感じ方は、
「年功序列ではなく若くても登用するということ」
と理解することが多いようです。
さて、これは正しいのか?
「実力本位=若手登用」と勝手に解釈していないでしょうか?
採用案内にこういう内容も含まれていたらどうでしょう?
「当社は定年制を廃止し、実力ある方には長く勤務していただける環境を・・・」
定年というものは残酷な制度です。
能力がありながら、年齢という自分ではコントロールできない基準で仕事を奪われるのです。
小説「白い巨塔」の初めの部分で浪速大学第一外科主任教授東貞蔵がこれを感じます。
ただ、組織には新陳代謝も必要です。
だから定年制を設けることには合理性もあるのです。
それでも高い能力を有し、体力・気力とも十分の人に「辞めてもらいます」はどうなのか?
実力本位であれば、こういう人の処遇も十分でなければなりません。
若い人を早くから登用して育成することも大事です。
両方備えてこその実力本位でしょう。
「実力本位=若手登用」という捉え方は片面的すぎるのです。

さて、我々司法書士は?
完全に実力本位です。
合格期が早かろうが遅かろうが、年齢が若かろうが高かろうが関係はありません。
能力があれば依頼はひっきりなしです。
能力にはいくつかの要素があります。
1 法律に関する知識の質量・・・文字どおりです。
2 法律を使いこなす能力・・・法律を使って様々なスキームを組んだり、的確な文章表現をする力。
3 コミュニケーション能力・・・スムーズに協議や交渉をする能力です。
主なものはこれらでしょう。
特に重要なのは、3です。
2はあってしかるべきもの。これができない人はやや問題です。
1はなければならないもの。ここが弱い人は論外でしょう。
士業は「客商売」の面があり、3の能力を欠くと1と2が高くても依頼がこなくなります。
そして、これらは「合格期がいつか?」「年齢は何歳か?」といったこととはまったく関係がありません。
士業の世界には合格期の先後で序列化をしたがる人がいます。
ですが、これは外部からはうかがい知ることができないもの。
一般社会においては無意味な基準です。
年齢については、世間的に長幼の序を重んじる以上は意味があります。
ですが、これらは「実力」ではありません。
というように、司法書士の世界は完全実力主義なのでした。
老若男女が自身の能力を磨き続けることで依頼者のニーズに応える。
これが「実力本位」の本来の姿なのかもしれません。