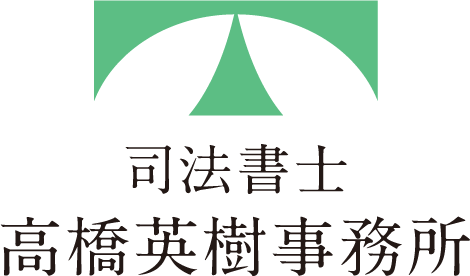レアな危急時遺言
最近のことです。
危急時遺言書について相談を受けました。
某士業の先生が、この依頼を受けて作成したそうです。
「いやあ、よく引き受けたなあ」
と感心しました。
家裁でも年に数件程度しか扱わないようです。
ある書記官によれば、田舎の支部だと数年に1回あるかないかの次元とのこと。
つまり、非常に珍しい方法なのです。
法定されている方法であはありますが、一般に知られているわけでもありません。
利用を思いつくのはプロ、つまりは士業の人くらいでしょう。
勿論、私もこの方法を知っています。
でも、私であれば、この仕事はお断りします。
その理由を述べる前に危急時遺言書について簡単に紹介します。
危急時遺言とは
Aに生命の危機が迫っています。たとえば、病気がかなり重篤というケース。
自らの手で遺言書を書くことができません。
この場合、Aは証人となるB、C、Dに対し口頭で遺言の内容を告げます。
3人の証人のうちBがそれを書きとります。ワープロでも構いません。
そして、Aに対しては勿論、CとDに対しても確認を行います。
CとDはその正確性を確認できたら署名と押印。
Bも署名と押印を行い完成です。
この後は、20日以内に家庭裁判所に対して確認を求める審判を求めて申立て。
Aが6か月生存した場合は失効ですが、亡くなれば、通常の遺言書同様です。
家庭裁判所で検認手続を行うのです。
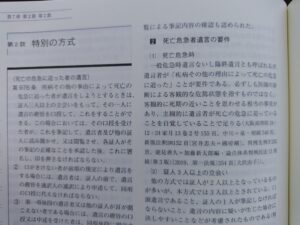
やらない理由
私が回避したい理由は次のとおり。
たとえば、Aが全財産を配偶者Xに相続させる旨を述べたとします。
こういう場合、Xは子Yから遺留分侵害額を請求されるかもしれません。
それは仕方がないのでしょう。
でも、遺言書そのものの有効性にYが疑義を呈する可能性が高いのです。
つまり、相続人間のトラブルに巻き込まれ、Yから
「Xと結託してYの権利を侵害した」
とみられてしまう可能性があるのです。
上記の確認の審判もAの真意であることを明らかにするとまではいえません。
一応Aの真意のようであるーこれで家裁は審判を出します。
Aの死後の検認手続は、遺言書の有効性を認める手続ではありません。
飽くまでも形式が調っているかどうかの確認にすぎないのです。
病気が生命を脅かし、自筆証書遺言を作ることができないA。
はたして、「真意」を正確に述べることができるのか?
Yは、Bら証人に対して疑惑の目を向けるでしょう。
ゆえに、プロなら危急時遺言を回避したいと考えるのです。
司法書士の対応状況
ネット上では
「危急時遺言に対応する事務所は少ないけれど、自分の事務所は対応できる」
という宣伝めいた説明をみることもできます。
そういう記述を読む私は「頑張ってください」とエールを送るのみです。
また、以前にも実際にやったという経験談を耳にしたことがあります。
「父が危ない。すぐに来て!」
こういう要請を受けて駆け付け、危急時遺言書を作成したという話でした。
駆けつけた段階で、依頼者により証人は用意されていたのか?
「危ない」状況で真意に基づく遺言をすることが可能なのか?
色々な疑問を感じます。
仮に、証人が3人揃っていても、遺言者の真意に疑いを抱く余地は残ります。
普通は受任しないケースだと思われます。
多くの司法書士は、危急時遺言には消極的です。
法律を扱う仕事をしている立場としては、当然かもしれません。